
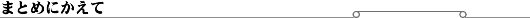 |
人は、決して一人では生きられないものです。それは、人のみならず、この地球に住む全ての生きものに共通することではないでしょうか。自然界における食物連鎖においても、種を限りなく未来に引き継ぐため、ある意味では互いの共生が連鎖的に存在すると言えましょう。
「まち」を生きものとして捉えた時、そうした高齢者と地域との関わりもまた、人が人としてあらゆるものを生き継ぐための欠かすことのできない大切な営みのひとつなのだと考えます。それぞれが持つ地域固有の文化・歴史・人物・産業および環境などのあらゆるものを後世に残し伝えること、こうしたまちの文化遺伝子を大切に思う心や思想をあらゆる角度から編集し、蓄積していく作業こそコミュニティ・アーカイブズの実践そのものであり、本事業のコンセプトであります。
平成2年に発行した「あすへの遺産:明治・大正・昭和を語る」は、桐生市老人クラブ連合会の会員全員が企画し、取材からワープロ、写真、カット、編集にいたる作業を高齢者のパワーのみで完成させました。
今回の「新・あすへの遺産:桐生織物と撚糸用水車の記憶」は、桐生市老人クラブ連合会と「情報化を手段としたまちづくり」を目標として地域活動に努めるNPO法人桐生地域情報ネットワークが協同作業で製作したものです。作成にあたっては、地域における高い見識をもつ編纂運営委員のアドバイスを受け、取材、執筆、編集等については、前回同様、高齢者自身が行いましたが、これに加え群馬大学工学部の学生とNPO法人桐生地域情報ネットワークの若い世代がインタビュー等に積極的に参加し、多世代交流を軸とする新たな取り組みをしてきました。
最新の情報技術を応用したアーカイブズづくりのチーム自体が多世代交流を軸とすることで、各々の多様な経験と知識の共有化が図られ、世代間交流により若者の好奇心が拡がってくれたことも大事な目標のひとつでありました。地域の歴史・文化・人材・技術など貴重な智恵と経験を有する高齢者を尊い、協働作業の中から、地域固有の文化遺伝子を集積し、後世に引き継ぐ姿がそこにありました。
このように、高齢者の活躍の場としてのアーカイブズ作成への参画は、社会全体としてみても公益を増進することに直結するものと言えましょう。
本冊子製作の過程において、生糸からお召し縮緬の生地ができるまでの全工程の実物を含んだ資料も完成しました。大正時代に一世を風靡したお召し縮緬の着物も、今では古着屋さんの店先でしか見られなくなってしまいました。
本冊子に添付されたロゴマークのカット生地は、インターネット上でデザインの公募を行い、北は北海道から南は沖縄と全国規模で応募があり、この中から、編纂運営委員会によって最優秀となった東信慶さんのデザインをもとに、運営委員会の一人でもある織物参考館「紫」館長の森島純男さんが(株)森秀織物で製作した「お召し縮緬」です。大分県湯布院の一村一品運動以来、地域おこしとしての産業活性化のヒントになることを期待して止まないところであります。産業をつくりだすことは、新品種をつくる育種に似てセンスが問われると思います。アーカイブズづくりの中での世代間交流を通して、若い世代に醸成される興味や好奇心が、彼らのセンスを磨き新たな発見を助成する可能性を生み出してくれると確信しています。
平成2年、桐生老人クラブ連合会会長の田所富士太郎さんは「あすへの遺産」の中で、「私達高齢者が、この恵まれた長寿社会の中で、長生きしてよかったと心から思える生きがいを自分で見つけることは、若い世代の人達と一緒になって生きてゆくということではないでしょうか。」と多世代交流の大切さを唱えていました。
また、編集部長の横山岩雄さんは「編集を終わって」の中で、「この文章を読んだ人達が、この中から語り草の種をひとつひとつ蒔いて下さるならば、この伝承はより広く、より深く、そしてより永く伝えられて行くことを信じて疑わない。」と伝承活動の継続を念じています。
こうして「多世代交流の伝承活動」に想いを寄せた我が先輩諸氏の意思を、本事業で継承し得たかと問われれば、「諾」と答えたいところでありますが、それは、いま、まさに始まったばかりなのだと言えましょう。 |
|

|