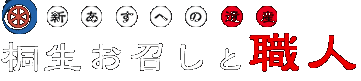| ――保倉さんがこのお仕事に関わっていたのはいつ頃なのでしょうか?
保倉 そうですね、中学生のころはもう親父と一緒に働いていましたね。高校も大学も、籍は置いていましたが独学でした。職人が学校に通うというのは、人に嫌な感じを与えるので内緒にしていました(笑)。
――当時、多い時でこの仕事をされていた方はどのくらい居ましたか?
保倉 わずかな期間で大きな変化がありましたし、ほかの家のことはよくわかりません。私の家に限って言うならば、私がこの世界に飛び込んだ時が一番人が多くて、従業員が15名程でしょうか。その時期は私の家に限らず、どこでも悪くないようでしたね。あとは凄惨なもので、今はどうしようもないですね。仕事はないと思います。仕事があるのに辞めたのは私だけですよ(笑)。
(持ってきた紋図を広げて見ながら)
これは昭和41年のものですけど、これが紋図というものです。いろんな呼び方があるんですけど、教科書には意匠図と載っています。私共のことは皆、図案屋と言っていました。ですが、最初から最後まで全部やっている人はいませんでしたね。図案を描くだけの人、図案の商いも行う人、織物に限らず、いわゆるデザインをなんでもする人と様々でしたね。
で、この2枚の紋図をあわせると上下の模様が繋がります。これが紋織りお召しの紋(模様のこと)になります。これらのアイデアは「このようなものを作りたい」という発想がなくてはいけないわけです。現実問題として下描きは省略して、みんなの意見を聞きながら、図案を描いては直してゆくんです。まぁ図案屋は何度も描き直した方がお金になりますからね(笑)。「花をもっと大きくしますか?」と聞いて、その意見を元にまた描き直したりしてね。
――例えば機屋さんから「この図柄がいいからこれを織物になるよう描いてくれ」と言われることはあったのですか?
保倉 そもそもそういうことが求まれてくるものは二流品でして(笑)、もうちょっと良いものを作ろうという場合は元絵の相談から始まります。
作業の手順としては、大元の絵(オリジナル図案)がありますよね、あの頃はただ図案と言っていたかもしれません。それを正絵にします。私たちはみんな下図と言っていますけど、それに基づいて増し絵を行って、紋図に拡大してゆくわけです。最近では正絵からコンピュータで織れるようになりましたね。
――保倉さんの場合も、元絵から描いていたのですか?
保倉 元絵のイメージをこちらで受け取って正絵に描き表すというのが基本なんですが、実際にはそうではなくて、こちらの持ち合わせているものを向こうが求めて、それを描き表すというスタイルでした。また、正絵を紋図にしながらも変更してゆくこともあるんですよ。要するにそういうことをやるのを図案屋と言ったんです。教科書の上では工程別になっていますけど、マニュアル通りにはいかなかったわけです。
ジャカード織りが入ってきてからは、一般工員ができる仕事になったものの、それ以前は全て暗記でした。どういう方法で織っていたかはわかりませんが、暗記してやっていたことだけは事実です。どのくらいかというと…この紋図を見ると、(紋図の方眼を指差しながら)ココからココまでなら、どんなに省略しても600ぐらいはあります。それをまず丸暗記するわけです。それを何かの方法で織るわけですね。
桐生で紋織りが発生したときから図案屋をやっていますが、当時は細い筆と定規で溝引きして、和紙に直線を何本も描き、さらにそこに目盛りを描き込むというようにして方眼紙を描くことから始めていました。京都は8等分、桐生は12等分でしたね。
それが大正の後期でした。その頃から桐生の紋織りお召しが始まり、戦争で一旦下火になって、戦後に復活して全盛期を迎えるわけです。紋柄(模様)が付くことによってお召しが有名になったんです。
(ある紋図を指し示しながら)
これなんかは当時、お召しの柄として織られたものです。森秀さんで織ったものですね。
――これも織り上がると連続する小柄になるんですか?
保倉 ええ、これはしっかりと繋がります。この紋図の正絵が見つかりませんが、それを見ながら図柄を大きくする作業を増し絵と呼びます。これもやはり記録としては残した方がいいと思いますね。織物は機械で作りながら、更に作業しやすいように工夫しながら変わってゆくわけです。
ところが、いつのまにか昔は手機で織っていたような話になっているんですよ(笑)。桐生は手機なんかじゃありませんからね。力織機がこれだけ使えたということが正しい記録であり知恵なんです。手機は原始的なもので産業とは呼び難いものではないでしょうかね。
手前味噌な話になりますが、正絵を拡大して、綺麗に描いてゆくのは大変な技術なんですよね。私は自作した拡大機を使っていましたが、これを使うと多少のいたずらもできるんです。例えば「この花だけ大きくしよう」とか、逆に「もっと小さくしよう」とか。もう壊しちゃいましたけど、かなり大きなものでした。当時描いた拡大機の設計図も残っています。これは当時としては大変ショッキングな出来事で、ほかの職人から圧力がかかったりしましたね。私はこれをやって儲けさせていただきましたが(笑)。
その後、拡大機が発売され、非常に便利になりましたから、色々なデザインが次々とできたんでしょうね。そうでないと、高度な技術をもった一人がやることになっちゃうんですよ。私のところでは全盛期の頃は職人を集めて紋切りもやっていたんですよ。一緒にやったほうが早いですから。京都はみんなそうなんです。京都の真似をしてやっていました。
――では、逆に紋切り屋さんでデザインをやっていた方はいましたか?
保倉 それをできる人はいませんでしたね。私も紋切りはできませんでしたので、職人さんを集めたんです。私は機屋さんとも現場の人とも相談して、さらに職人さんたちとも相談してというように、一つの組織の形にしていたんです。その方が得でしたから、そうやっていましたね。
――ひとつの工房という形式でお仕事されていたわけですね。
保倉 はい、私はデザイナーであったと共に、そういう点ではビジネスマンでしたね。でもデザインというのはビジネスと繋がらないとできませんからね。
――こうやって図案を描いているときに織り上がりの形は浮かんでくるものですか?
保倉 それはもう一体ですね。常に出来上がりの様子を思い浮かべながらやっています。それだけの知識、技術がないとできない仕事ですね。まぁ職人というほどのところまで技術がある従業員が集まれば良いんですけれど、寄せ集めで誰でも働けるようにしていました(笑)。何も知らないでやっていた人もいましたよ。そういう場合は足りない部分を私が補っていました。私の仕事はそういうことでしたね。なるべくコストを低く抑えて、上手に良いものを作った方が効率的ですからね。
――デザインを見るだけで「これは織物になり易い」とか、「なり難い」とかわかるものですか?
保倉 そういうことを考えることも当然ありますけれど、機屋さんに私たちの仕事を活かしてもらうのが主流でしたから、改めてそれを考えるということはありませんでしたね。そりゃ、とんでもない注文を受けることもよくありましたよ。例えば初めて人工衛星が飛んだ時なんか人工衛星描いちゃおうとかね(笑)。どれだけ売れたかは知りませんが、そういう意味で、今おっしゃったようなことを考えることもありましたけどね。
――デザインするときに織り上がった状態を想像するということでしたが、さらにそれを仕立てて誰かが着物を着ているところまでを想像することもあるのですか?
保倉 着ているところや着ている人まで想像できると大変良いんですけど、そこまでは考えないものですね。単に柄を想像して、こんなのが受けるんじゃないかってのを考えていましたね。
――ヒット作というようなものはありますか?
保倉 そういうのはね、やっぱりあるんですよ。ですから、デザインの資料も機屋さんのほうにはあるかもしれませんが、実質的には私たちには関係ないことですから覚えていませんね。
――デザインに関しての著作権みたいのものはないわけですか?
保倉 著作権はあるはずなんですけどねぇ(笑)。
――今までの仕事の中で特に印象深い柄はありましたか?
保倉 具体的にはこの柄というのはないんですが、森秀さんで夏冬用に約400柄作って、それが比較的売れていたのを覚えています。森秀さんのところは短くて、10年ぐらいしか働いていなかったんですけどね。
――すごく下世話なことをお聞きしますが、当時どれくらい稼げましたか?(笑)。つまり、反物の金額(価値)に対して、この工程が全体のどのくらいの価値を占めていたのかということが知りたいのですが。
保倉 これはパーセンテージじゃないとわからないですね。例えば、逆算してピンからキリまであるとして、1反が5万円というものがあったとします。で、模様ってのは小さな模様だと私たちの手間はかなり少ないんです。大きなものになりますと大変な手間になりますね。だからといって5万円が相場なら5万円(当時、以下同じ)なんですね。一番安いといっても3千円、4千円は頂いていたと思います。高いものは2、30万円ぐらいでしたかね。
――デザイナーとして今、それだけのお金をもらって仕事をしているというのは、ごく一部の人達だと思いますね。そういう意味において、当時はデザイナーがすごく大切にされていた気がしますね。 |